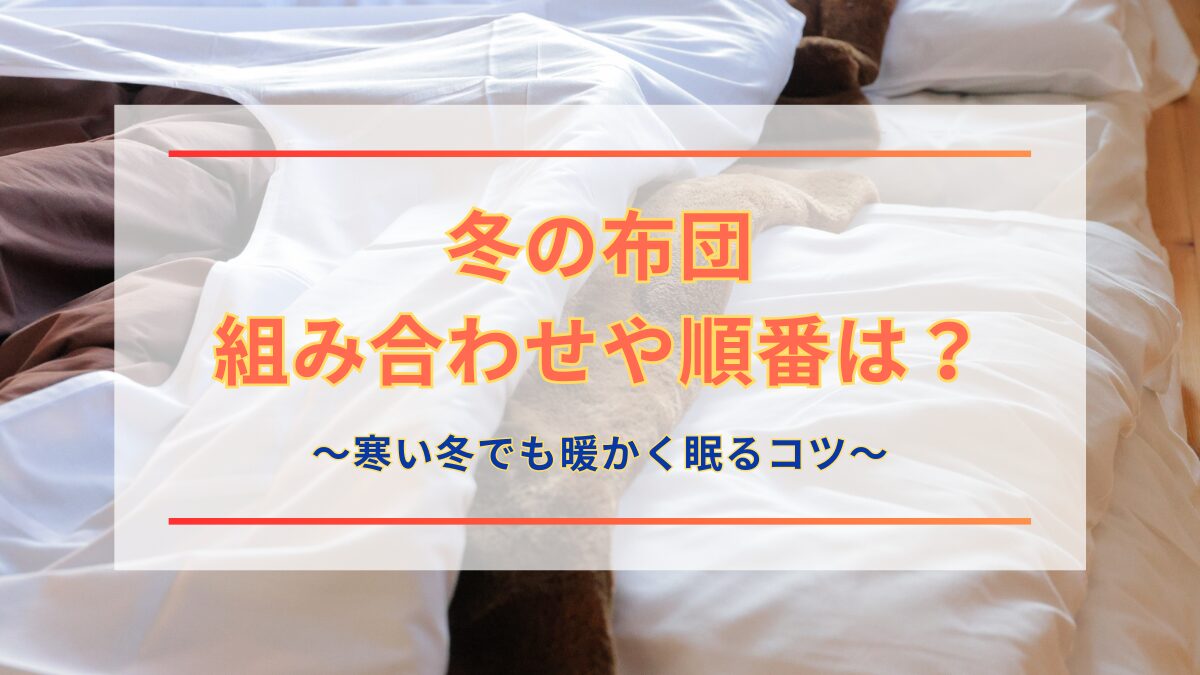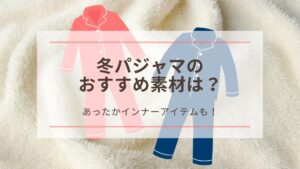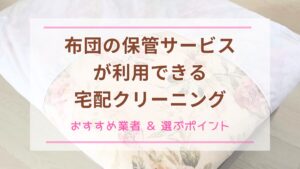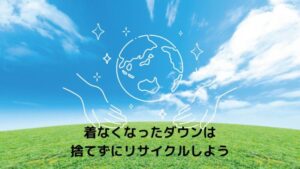寒さが厳しくなる冬の夜。
「布団に入ってもなかなか温まらない」
「夜中に寒くて目が覚めてしまう」
「夜中に布団がズレてしまって寒い」
そんなお悩みを感じることはないでしょうか?
 杏奈
杏奈そんな方でも、寝具の組み合わせ方や選び方を見直すだけで、朝までぐっすりと暖かく眠れる環境を整えられますよ。
この記事では、
- 羽毛布団と毛布の重ね方の基本
- 敷パッド・パジャマ選びのポイント
- 布団のお手入れ方法
まで詳しく解説します。
今日から誰でも簡単にできる「暖かく眠れる寝具の工夫」を取り入れて、冬の夜を快適に過ごしましょう。



寒がりさんの参考になったら嬉しいな♪
目次 |
暖かく眠れる寝具の組み合わせは?
冷え込みが厳しい冬の夜、朝までぐっすりと、暖かく快適に眠りたいものですよね。そのためには、寝具の組み合わせ方がとても重要です。
- 羽毛布団(冬布団は充填量1.0kg以上※)
- 毛布(アクリル・ポリエステル・ウール・カシミヤ等)
とても簡単ですので、この機会に羽毛布団と毛布の重ね方を覚えてしまいましょう。
また、下に敷く寝具やパジャマにも少し気を配ってみてください。解説していきますね。
羽毛布団と毛布の重ね方
羽毛布団と毛布の重ね方ですが、毛布が「天然繊維」か「合成繊維」かで異なります。
天然繊維の場合は通気性や吸湿性に優れているため、直接肌に触れる側に毛布を重ねると良いでしょう。
天然素材の毛布の上に、羽毛布団を重ねる


一方、毛布が合成繊維の場合は、吸湿性や保温性に優れた羽毛布団を肌に近い側に持ってきます。毛布は、羽毛布団の上に重ねます。
羽毛布団の上に、合成繊維の毛布を重ねる





あまり重い毛布だと羽毛布団の空気の層がつぶれてしまうから、軽めのものを選んでね。
羽毛布団が肌側に来ますから、布団に入る時のひんやりした感触が嫌な方もいるかもしれません。そんな場合は、羽毛布団のふとんカバーを起毛のものに変えるなど、工夫をしてみてくださいね。
体の下には何を敷く?
冬の冷気は下からやってきます。そのため、布団や毛布だけでなく、体の下に何を敷くかも重要です。
- 敷布団+冬用敷パッド
- マットレス+敷き毛布
- 冬用敷パッド+毛布
体の下には「敷パッドや毛布・電気毛布」を使うことで、底冷えを防げます。特に寒い季節は、起毛素材やウール系など保温性の高い敷パッドを加えると効果的ですよ。


冬のパジャマは何を着る?
パジャマの存在も重要ですよね。
直接肌に身に着けるパジャマは、寝具による保温性の最終調整をする役割を果たします。
冬のパジャマは、繊維の中に空気を含み、軽く暖かい素材ものものがおすすめです。具体的には、保温性と通気性を備えている厚手の綿素材が冬のパジャマとして最適です。
熱くなりすぎるフリース素材は、就寝中に寝汗をかいて、かえって睡眠の妨げになることも。
冬布団の環境がしっかりと整っている場合は、ムレ防止の観点から、吸湿性を意識してパジャマを選ぶと良いでしょう。
おすすめのパジャマ素材やインナーアイテムについて書いています↓
冬の寝具選びの基本ポイント
冬の寒い夜に暖かく快適に眠るためには、住環境や、体質に合わせた寝具選びが重要です。
- 室温が低い場合は、羽毛布団のように保温性・吸湿性に優れた素材を選ぶ。
- 部屋の気密性が高く暖かい場合は、やや軽めの掛布団や毛布で調整する。
- 冬でも汗をかきやすい体質の方は、天然素材の通気性が良いものを選び、寝具内の湿気を逃がす工夫をする。



使っている寝具を少し変えることで、快適さがさらに増す場合が多いですよ。
掛布団


寝具の中で最もパワーを発揮する掛布団に何を選ぶかで、冬の就寝時の暖かさが変わってきます。
羽毛布団
冬の掛布団で最も暖かいのは、羽毛布団です。
- 軽い
羽毛布団は非常に軽く、体への負担が少なく寝返りもしやすいです。 - 暖かい
羽毛は空気の層を多く含み、暖かい空気を逃しにくく、優れた保温性を発揮します。 - 吸湿・放湿性が高い
放湿性が高く余分な湿度をため込まないため、常にさらさらで快適さを保てます。 - 耐久性が高い
大切にメンテナンスすることにより、品質の良いものであれば10~20年使用することができます。
とはいえ、羽毛布団の品質や価格帯はピンキリです。廉価なものについては、残念ながらさほど暖かさが感じられないかもしれません。
羽毛布団の「羽毛」は、水鳥の胸にある綿毛のような部分を採取したものですが、鳥の種類や生息地によって品質にランクがあります。
【羽毛布団のランク】
| 保温力 | 備考 | |
|---|---|---|
| ダック | 比較的安価で初心者におすすめ | |
| グース | ダックより保温性が高く高価 | |
| マザーグース | 羽毛布団の中で最上級クラス | |
| アイダーダック | 天然もので非常に希少、最高峰の保温性 |
ひと昔前では手ごろな値段で購入できましたが、貴重な天然資源であるため、現在の価格帯は上昇しています。今使用していない上質の羽毛布団が自宅にあるなら、リペアして大切に使用するのもおすすめです。
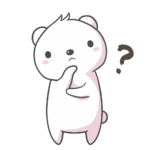
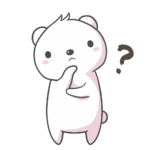
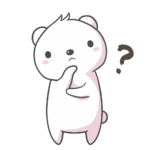
羽毛布団に使われている羽毛の種類って、どうやってわかるの?



布団の洗濯表示のタグに書いてあるわよ。
その他の掛布団
羽毛布団の他には、綿わた布団や真綿(まわた)布団、合繊布団などがあります。
- 綿わた布団
-
綿花から採れる天然素材で肌触りが良く温かいですが、羽毛布団に比べると重めで、通気性はやや劣ります。
一昔前はどの家庭にもある一般的な布団でした。
- 真綿(まわた)布団
-
蚕の繭からとれる絹(シルク)をわた状に加工したもので、軽さや柔らかさ・しなやかさが特徴です。
保温性や吸湿放湿性にも優れ、上質で快適な寝心地が得られます。昔ながらの高級布団です。
- 合繊布団(ポリエステルなど)
-
軽くてふんわりしており、抗菌防臭、防ダニ、消臭、吸汗吸湿など高機能なものが増えています。
洗濯しやすくお手入れが簡単で比較的安価ですが、保温性や耐久性は天然素材に劣ることがあります。
毛布・敷パッド


毛布や敷パッドは、暖かさや快適さをさらに高める役割を担います。
- 毛布
-
毛布には
- 1重毛布
- 合わせ毛布(二重毛布、マイヤー毛布)
があります。
合わせ毛布は2枚の生地を縫い合わせて1枚にしているため厚みがあり、冬の寒さが厳しい時期にピッタリです。その分重量感があるため、好みが分かれるところです。アクリル・ポリエステル等- 流通量が多く、色柄が豊富で発色が良い
- 肌触りが良くなめらかな感触
- お手入れや洗濯がしやすい
ウール・カシミヤ等- 天然素材であるため、保温性と通気性、吸湿性に優れている
- ウールの独特のちくちく感が苦手な方は避けた方が良い
- 虫食いの可能性もあるため、お手入れを怠らないようにする必要がある
- 敷パッド
-
冬用の敷パッドは、ベッドのマットレスや敷布団の上に敷きます。
冬用の敷パッドは、ボアなどの起毛素材が一般的。寒がりさんには電気敷き毛布など、暖かさを重視したものが人気です。
布団カバー


羽毛布団のカバーは軽くて通気性・吸湿性の良い天然素材(綿、シルク、麻、リヨセルなど)が理想的です。
暖かい空気の層をため込んで保温性保つ羽毛本来の働きや、羽毛のふくらみを邪魔しないのが、天然繊維の良さですね。
冬用には、綿パイルやガーゼなど起毛しているものが、肌触りがふんわりしていて冷感がないのでおすすめです。
天然繊維に比べると通気性には劣りますが、保温性の高いフリースやマイクロフリースなどのカバーも、選択肢としては存在します。
暖房なしで快適に眠るための工夫とコツ


寒い夜、暖房なしで心地よく眠りに入るのは一見むずかしそうですよね。しかし、寝具をしっかり整えているならば、それほど難しい話ではありません。



ここでは、快適な眠りを手に入れるためのいくつかのアイデアをご紹介しています。
日中や寝る前のひと工夫で、暖かく快適な入眠を
快適な睡眠には、前提として規則正しい生活を送ることが必要です。
その上で、寝る前に軽いストレッチをしたり、寝具を温めておくことで、快適な入眠を手に入れることができますよ。
- 起床後や日中に強い日光を浴びると、体内時計が調節されて入眠が促進される
- 寝る直前に深呼吸や軽いストレッチで血行を促進し、体温を高めておく
- 寝る少し前に、布団乾燥機で布団を軽く温めておく
- 入眠までの間、湯たんぽや電気毛布で温める
寒い冬の夜は寝る前にあらかじめ寝具を温めておき、入浴後は1~2時間以内に就寝するようにすると、寒さを感じず暖かい状態で眠りに就くことができます。
さらに、寝る前のストレッチや深呼吸で体の状態を整えることで血流が良くなり、体が温まってリラックス感を感じながら布団に入ることができるでしょう。
その他、
- 寝る前にはスマホやタブレットを見ない
- リラックスできる香りで安らぐ
- 就寝中は室内をできるだけ暗くする
──など、他の季節にも応用できるさまざまなアイデアを試してみてください。
【参考】
厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」
日本寝具寝装品協会「眠りと健康」
夜中に布団がずれないようにする
寝返りをうつたびに布団がずれて寒くなるのは、よくある悩みですよね。
布団と毛布のズレを防止するための便利グッズも販売されています。
掛け布団とカバーのずれも、寒さを感じる原因かもしれません。
カバーが大きすぎると中で布団が動いてしまい、暖かい空気が逃げてしまいますので、布団にぴったり合ったサイズのカバーを選びましょう。
(5~10cm程度の誤差なら大丈夫です)
布団の四隅にあるループと、カバー内の紐をしっかり結び付けることで、ずれを防止できます。
冬布団の普段のお手入れ方法
冬布団は比較的長い期間使用するため、快適さを保つためには定期的にお手入れをしてあげることが大切です。
自宅でできる、普段の簡易なお手入れ方法をご紹介します。
陰干し(天日干し)をする
布団に溜まった汗や湿気を飛ばすため、週に1度程度を目安に陰干し(もしくは天日干し)を行って、布団の内部をしっかり乾燥させましょう。
- 晴れた日の午前10時から午後3時の間に、布団を片面1~2時間ずつ陰干しする
- 羽毛布団を天日干しする場合は、直射日光に当たらないようカバーをつけたまま干す
湿気を外に逃すことで、布団本来の保温性が高まり、においの軽減にも役立ちます。
カバー類はこまめに洗濯を
直接肌に触れる布団カバーは、汗や皮脂がついて汚れやすいため、清潔さを保つことが重要です。
週に一回以上洗濯を行って、清潔な状態をキープしましょう。特に汗をかきやすい方は、こまめな洗濯が必要です。
洗濯の際は洗濯表示を確認し、素材に合った洗い方で優しくケアしてください。清潔なカバーが布団本体の寿命も延ばすポイントとなりますよ。
布団のクリーニングについて


同じ布団を長期間使用していると、家庭のケアでは限界を感じることがあります。
布団のかさが減ってボリュームがなくなってきた、カビやホコリ、汗などのにおいやシミが気になる、ベタベタして何となく不潔な感じがする……。そんな時は、布団のクリーニングの出番です。
クリーニングに出すことで、布団の状態が驚くほど良くなり、買った時のような清潔感やフカフカ感が再び感じられるでしょう。
布団をクリーニング(丸洗い)するメリット
布団のクリーニングとは、ドライクリーニングではなく、たっぷりの水と専用洗剤を使って布団内部の汚れまで落とす「丸洗い」のことです。
布団を数年ごとに定期的にクリーニング(丸洗い)することで、汚れをしっかり除去でき、清潔な状態をキープできます。
布団がフカフカになると、布団本来の保温性も復活します。
自宅で洗うのが難しい布団も、クリーニングに出せばしっかりケアできますので、長く快適に使いたい方にはおすすめの方法です。
布団を丸洗いするなら宅配クリーニング
布団をクリーニングに出すと言っても、布団を取り扱っているクリーニング店が近所になかったり、第一、大きくてかさばる布団を持ち運ぶこと自体が大変ですよね。
布団のクリーニングは、自宅まで取りにきてくれ、クリーニング後に再び自宅まで届けてくれる「宅配クリーニング」が圧倒的におすすめです。
- 布団の持ち運びの手間や時間が短縮できる
- 大切な布団を丁寧に扱ってくれるクリーニング店を全国から選べる
- 布団の悩みが解消される
- 布団がフカフカになる



布団は大きくてかさばるのでクリーニングが大変なイメージですが、宅配だと手間いらずで簡単です。ただし、日数には少し余裕をもってくださいね。



おすすめの宅配クリーニングが気になる方は、下記の記事を参考にしてみてね。
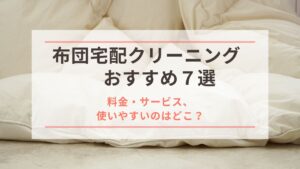
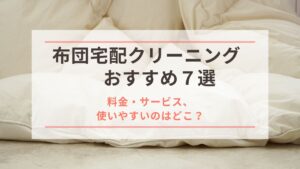
まとめ
暖かく眠れる寝具の組み合わせや、それぞれのアイテムの特徴、また、布団のお手入れなどについて解説しました。この記事でご紹介した内容がひとつでも参考になれば、ぜひ実践してみてください。
- 体に近い側にウールなどの天然繊維の毛布を重ねると、吸湿・発熱効果でより暖かく快適に
- 合成繊維の毛布の場合は、羽毛布団の上に重ねる
- マットレスや冬用の敷パッド・カバーなどを組み合わせて、底冷え対策や寝心地アップも
また、布団は長期間使うと汗や汚れが蓄積するため、保温性が落ちてしまいます。
丸洗いでしっかり清潔に保つのが快眠への近道ですので、布団のお手入れをしていない方は、利便性の高い宅配クリーニングを、ぜひ一度利用してみてください。
保管ができる羽毛布団クリーニングについて書いています↓
貴重な天然資源である「ダウン」を、SDGsの観点から書いた記事です。↓